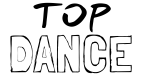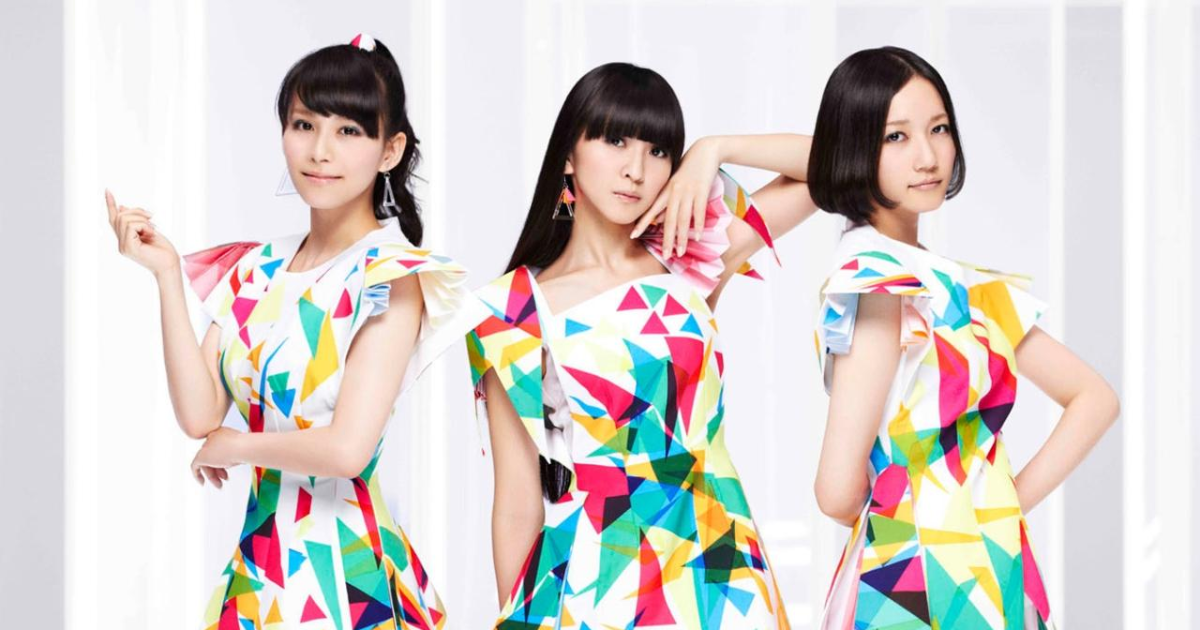北村仁さんは、株式会社ユーディフル代表取締役で、手話ダンスの普及を目指して活動するダンサー・パフォーマーです。障害の有無に関係なく、誰もが「表現する楽しさ」に触れられる場を作っています。また、ギネス記録への挑戦や、障害者の雇用支援、文化づくりなど幅広い活動を展開しています。
「音楽を諦めなくていいんですね」 そう語った難聴の方の一言が、北村さんの人生を変えたと言います。
今回はそんな北村さんに、手話ダンスとの出会い、ギネス挑戦の裏側、そしてダンスの未来についてたっぷりお話を伺いました。
手話ダンスとの出会い
「この活動をやろうと思ったのが、難聴の方から『音楽を諦めなくてもいいんですね。自分を許すことができました。』っていう風に言っていただいたことがきっかけです。」
手話ダンスを始めたきっかけを尋ねると、北村さんはそう語ってくれました。
「聞こえる・聞こえないに関係なく、『したい』という気持ちはみんな同じだと思うんです。」
世間の人には、聴覚に障害がある方にとって、音楽は「遠い存在」と思われがちです。しかし、実際に聴覚障害のある方(ろう者・難聴者に話を聞いてみると、ライブに行きたい人も、カラオケが好きな人もたくさんいることに気づいたそうです。その中で、音が聞こえなくても「音楽を目で見て、体で感じれる」手話ダンスは、新しい希望の形として機能するとのことです。
「車椅子で生きる人が、それぞれの方法で自由を感じたいように、音楽やダンスにも『自分なりに楽しみたい』という想いがあると思うんです。」
「そして、聞こえる、聞こえないに関係なく、同じ楽しい空間にいることが両者理解につながると思う。だから、そういう文化を作っていきたいなって。」
これこそが北村さんが手話ダンスをやろうと思ったきっかけだそうです。
手話ダンスの衝撃
北村さんに、これまでの活動の中で心に残っている手話ダンスのパフォーマンスについて尋ねると、こんなエピソードを話してくれました。
「僕が手話ダンスを始めた頃に、すでに耳の聞こえない方で手話ダンスをされている方がいたんです。その踊りを初めて見た時に、すごく衝撃を受けました。」
当時、北村さんは「手話ダンサー」を名乗りながらも、まだ実際に聴覚障害のある方との接点はなかったといいます。そんなときに出会ったパフォーマンスが、彼の中の価値観を大きく変えていきました。
「聴こえる・聴こえないに関係なく、感情がこんなに伝わるんだと感じましたね。それを見て、自分のダンスに対する考え方も大きく変わりました。」
この出来事は、後に彼の活動の核となる「手話とダンスで世界をつなぐ」というテーマに、自然とつながっていったのです。
ストリートダンスから手話ダンスへ
もともと北村さんは、ストリートダンスの世界で活動されていました。しかし、ある時、「ダンスをやめようかな」と思った時期があったそうです。
そんな中で出会ったのが、手話ダンスを主軸に活動するチームでした。
「そのチームがニューヨークのコンテストに挑戦して、そこに助っ人として呼ばれたんです。」
助っ人参加だったはずが、そのまま正式にチームの一員となり、活動を続ける中で手話ダンスの世界にのめり込んでいった北村さん。そのチームを7〜8年前に卒業し、現在に至るまで、自身のスタイルを貫きながら活動を広げています。
そして、手話ダンスの歴は気付けばもう15年。
「切っても切れない関係になりました。」と答えてくれました。
手話ダンスは「歌詞」と向き合うアート
手話ダンスの制作で難しさを感じるのは、依頼された楽曲の内容によっては、手話での表現が成り立ちにくい場合があることです、と北村さんは語ります。
「意味がしっかり伝わる歌詞ならいいんですけど、最近のボーカロイド系とか、Adoさんのような『言葉遊び』系の楽曲になると、手話では『伝える』より『当てはめる』になってしまって、記号遊びになってしまうんですよね。」
ダンスが自己表現の手段であるのと同じように、手話ダンスは言語としての「表現」を大切にしています。だからこそ、依頼内容によっては制作を断ることもあるのだそうです。
「手話ダンスって、リリカルヒップホップのもっと強い版、みたいな感じなんです。だから同じ曲でも一年後には全く違うものになる。その変化もまた、面白さであり難しさですね。」
全ての人に届けたい「手話ダンス」
北村さんは手話ダンスを「聾者や難聴者のためのもの」と限定しているわけではありません。
「聞こえる聞こえなく関係なく、要するに、ヒップホップ、ジャズ、バレエみたいに手話ダンスも普遍的なものにしていきたい。」
北村さん自身に障害はないものの、共に表現を楽しむ環境づくりを続けており、手話ダンスが性別、年齢、国籍、障害の有無を問わず、誰もが楽しめるダンスになることを目指しています。
ギネス記録に挑戦する理由
「ギネスってマニアックな記録が多い印象があるかもしれませんが・・・」と前置きする北村さん。
ですが、ギネスに挑戦するのには明確な狙いがあります。
「手話ダンスはまだ文化として確立されていない。だから『数字』でその存在を可視化したかった。そして、有名じゃないものをどう有名にするかを考えると、掛け算をしていかないといけないと思った。」
これこそが北村さんがギネス記録に挑戦する理由だそうです。
ギネスは「踊った人」ではなく「習った人」
北村さんが挑戦しているギネスは「手話ダンスを踊った人」ではなく、「手話ダンスレッスンに参加した人」だそうです。
「最初は踊った人数で申請しようと思ったんですけど、中国で1万人っていう記録があって、台湾で8000人の記録があるんですよ。そりゃあ無理だなって思って、考え直してみたんです。うちでは、ダウン症の子がいたり、知的障害の子がいたり、耳の聞こえない子がいたり、障害を持っていない子もいる中で、ギネスの規定が「踊る」になると、動きを揃えないといけないし、それは目的とは違うんですよ。」
北村さんは手話ダンスは正しく踊ることより楽しく踊ることこそが価値だと考えています。なので、あえて「手話ダンスに参加した人数」で記録をとってもらったそうです。
また、北村さんの教える手話ダンスレッスンでも生徒さんには「正しくやろうとしないで、楽しくやろう」と伝えているそうです。
毎年ギネスに挑戦したい
この手話ダンスの世界記録を毎年やりたいと思っていると言う北村さん。
「去年(2024年)は694人が障害の有無問わず、手話ダンスのレッスンに参加し、手話ダンスでみんなが繋がったんです。これはギネスワールドレコードさんに測ってもらったリアルな数字です。」
そして、このリアルな数を毎年更新していきたいそうです。
「僕としては手話ダンスって障害者と健常者が繋がったっていう公式な数だと思っているんですよね。」
「その上、参加者と世界記録に挑戦して、一緒に達成感を味わえたのが嬉しくて。」と彼は続けました。
今年は2000人がこの手話ダンスで繋がることが目標だそうです。
手話ダンス × ギネス
「手話ダンスって、すごくマニアックなものなんですよね。でも、ギネス記録ってなると、それだけでもう少しポピュラーなものに変わるんです。」と北村さんは語ります。
手話ダンスがギネスと掛け算されることで、行政や企業といった大きな組織ともつながるきっかけになるのだそうです。
「企業や行政とコラボすることで、障害のある人はもちろん、居場所がないと感じている健常者たちにも、多様な出会いや挑戦の機会を提供したいと考えています。」
ギネス挑戦はゴールではなく、「きっかけ」だといいます。その先には、情報や出会いが循環し、障害の有無を越えて人が自分の次のステップを見つけられるような社会を描いているのです。
ダンス業界の未来について
北村さんにダンス業界の未来についてもお聞きしました。
「ダンス業界の未来としては、個の時代になっていくと感じています。ダンスの上手さじゃなくて、自分の人間性っていうところがどんどん強調されていくんじゃないのかなって思います。」
北村さんは、ダンサーであると同時に「発信者」でもあります。
「健常者から見て、障害者にどう配慮したらいいかわからないという声を聞きます。でも、理解するための機会も知識も少ない。僕らは『障害の有無問わず、みんなしたいことは変わらない』ということを発信できる立場だと思います。だからこそ、ダンスって障害の有無を問わずできるんだよっていうようなことを証明していけば、社会もどんどん変わっていくんじゃないかなと思います。」
ダンスの枠を超え、障害のある人に寄り添う姿勢はまさに社会のお手本です。
ダンサーとして、次に目指すもの
北村さんが目標として掲げているのは、手話ダンスで一万人規模のギネスに挑戦すること。そして、手話ダンスを「ジャンル」として世界に広めていくことです。
「まだ世界には『手話ダンス』という文化が広まっていないので、日本だけでなく、台湾、中国などのアジア圏、そしてヨーロッパにも広げていきたいと思っています。」
そのためにも、まずは国内での認知を高め、多様な人が参加しやすい環境を整えることが大切だと語ります。
最後に伝えたいこと
最後に、読者の皆さんに向けて、北村さんからメッセージをいただきました。
「手話ダンスや、『障害 × ダンス』というテーマで悩んでいる人がいたら、ぜひ僕に連絡してほしいです!いい結果になるかはわからないけど、悪い方向には絶対いかないと思うので。」
悩みや迷いを抱えながらも、自分の「好き」に向き合おうとしている人たちにとって、北村さんの存在はきっと心強い味方になるはずです。
今後のイベント情報
北村さんが主催する「手話ダンスギネス挑戦イベント」が2025年9月6日に開催されます。
このイベントは外部の方もご見学・ご参加いただけます。!
詳細は2025年6月ごろ、北村さんのSNSやプレスリリースで公開されるそうです。少しでも気になった方は、ぜひフォローや体験レッスンから参加してみてください!